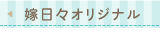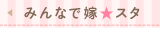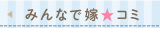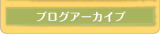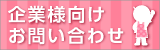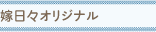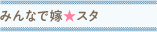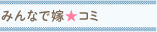誰似?
誰似?(3)
本日のお話は昨日の続きです。

おふくろは、市役所に勤めていた。
毎朝ぼくを見送ってくれるのは、おばあちゃんだった。
帰ってくると、家はいつも留守だった。
どうしても寂しい時は、畑にいるおばあちゃんの所まで行った。
子どものために有給休暇を取りにくい時代だったので
参観日も運動会も学芸会も
来てくれるのは、いつもおばあちゃんだった。
それでも、おふくろの言いつけを守り
学校での成績はよかった。
6年生では生徒会長もつとめた。

ほしいおもちゃ(めんこなど)やお菓子は
いつもおばさんが買ってくれた。
父親がいない不憫さは、やはり何も感じていなかった。
ただ、おふくろと自分の名字が違うのは面倒くさかった。
おふくろは離婚後、旧姓の「抹茶」に戻したが
ぼくの名字は父親の「バニラ」の姓のままだった。
母方と一緒に住んでいたが、戸籍は父方だった。
おそらくおふくろは、幼児期を過ぎたら
ぼくを父に返すつもりだったかもしれない。
父方は、地元ではそこそこの資産家でぼくはそこの長男になる。
幼いうちでは、どちらにつきたいか判断できないだろうと
成長を待って決めさせるつもりでいたらしい。
しかし、ここがまた複雑なことに
ぼくの父親は、おふくろと再婚だった。
実はぼくには腹違いの3人の姉がいるらしい。
前妻はその3姉妹の末っ子だけをつれた離婚したらしく
おふくろは、結婚と同時に2児の母親になっていた。
結局、その結婚生活も破綻し父親の元には前妻の2人の娘だけが残った。

その後、ぼくは父親のいるいないに関わらず
思春期を迎え、反抗期に入った。
小学校まで優秀だった成績もどんどん落ちていった。
何度も言うが、ぼくは父親を必要とはしなかった。
しかし、おふくろは必要と感じたのだろう。

父親は、となりの市で高校の英語の教師をしていた。
公立の進学校だった。
いけない高校でもなかった。
でも、そんなの関係ねぇ!だった。
結局、ぼくは地元の高校にすすみ
母親とはどんどんすれ違って行った。
相変わらず母親は不在で
おばあちゃんの作ったご飯を食べて
おばさんからおこづかいをもらって過ごしていた。
厳しい母親には、反感を持っていたが
おばあちゃんやおばさんとはうまくやっていた(…と、思う。)
そんなある日、部活の地区大会の試合会場で
去年の担任に会った。

その時の自分の心理状態は、はっきり覚えていないが
おそらく高木先生を驚かせるぐらいの
軽い気持ちで言ったと思う。
「K高校で英語を教えているバニラ先生は
ぼくの父親なんですよ。」
後にも先にも、父親の存在を認めたのは
この時が初めてだったと思う。
口にした後、急激に汗がでた。
しかし、高木先生の反応は自分のイメージと違っていた。
「あれ?バニラ先生には
2人の娘さんがいるだけと
聞いていたけど…」

はずかしいやら、情けないやら、みっともないやらで
その後のことは、あまり覚えていない。
やはり、自分には父親はいなかった。
そう確認しただけだった。
涙なんかでなかった。
自分が父親に1番近づいて1番遠ざかった瞬間だった。
(つづく)
誰似?(4)


この時代 ならではのムーブメントに
ぼくも染まっていった。

中学時代からの親友に
箱根アフロディーテに誘われた。
この頃のぼくは、ラジオの周波数を一生懸命合わせながら
ザ・フーやドアーズ、バニラファッジやクリームを聴くのが
唯一の楽しみだった。
…と言うより、それが全てだった。
箱根アフロディーテへは、ヒッチハイクで行った。
霧の中で聴いたピンクフロイドに
心のそこから感動した。

その後は、どんどん音楽にのめり込んでいき
バンドも結成した。
地元で有名ミュージシャンがコンサートをすると
その前座をつとめるようになった。
母親は何度も学校から呼び出しをくらっていた。
なんとか高校は卒業したものの
もう2人がまともに会話をすることもなくなっていった。
しかし何かの本を探していた時、
洋裁の本や公務員読本に混じって母親の本棚から

がでてきた。しかし…

これが勝手にした唯一の母親との会話だった。
さてその頃、ある田舎の片隅で

と、くったくない小学4年生の女の子がいた。
後にこの少女が、クリーム少年と結婚することになろうとは
ゆめゆめ思いもしない。
(もう少し、つづく)